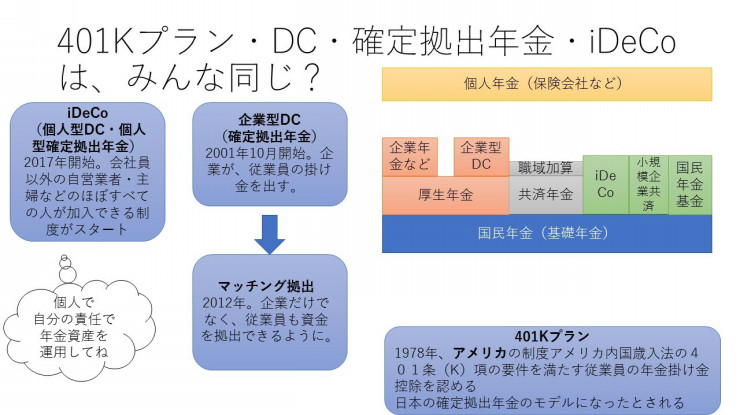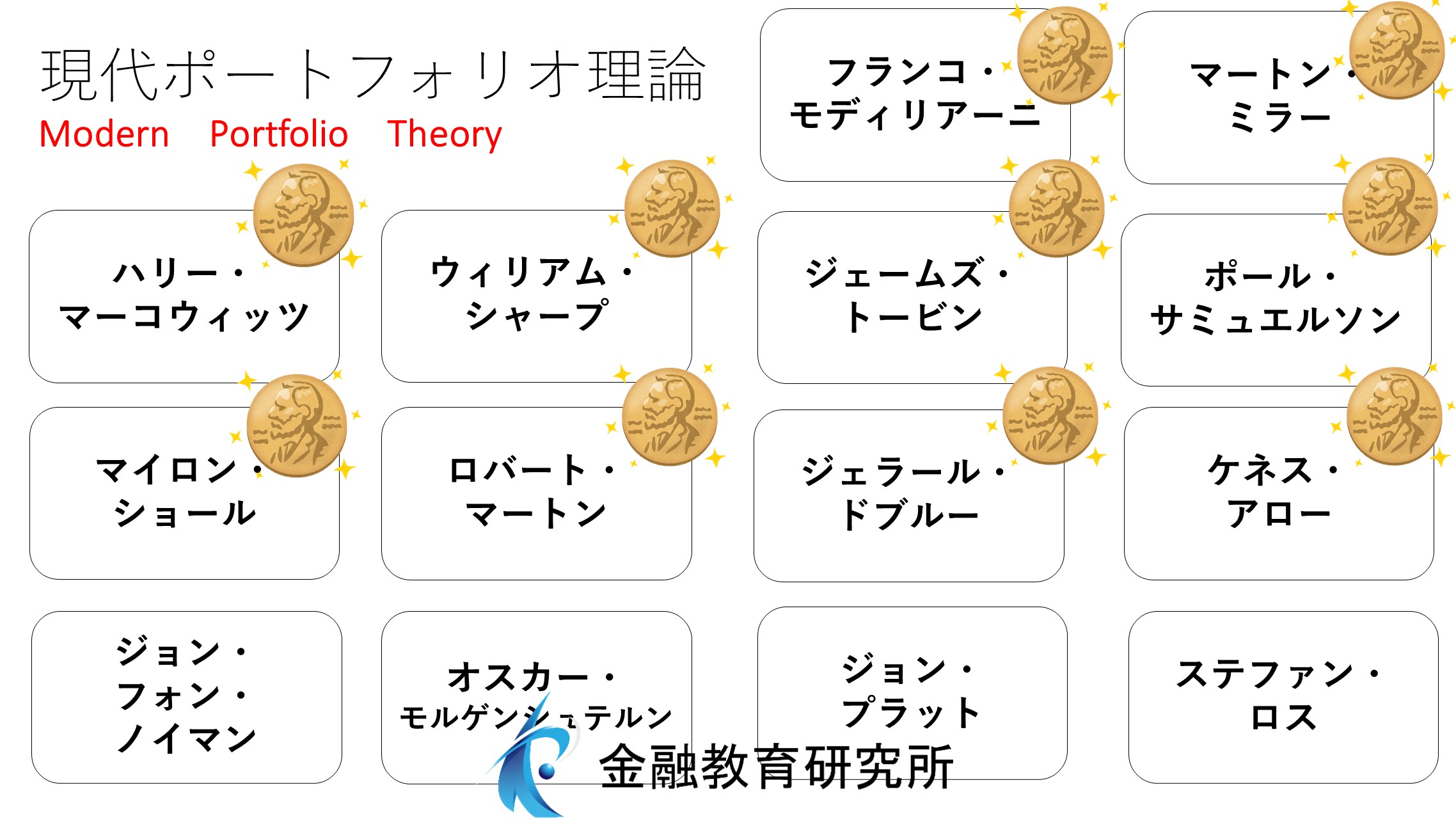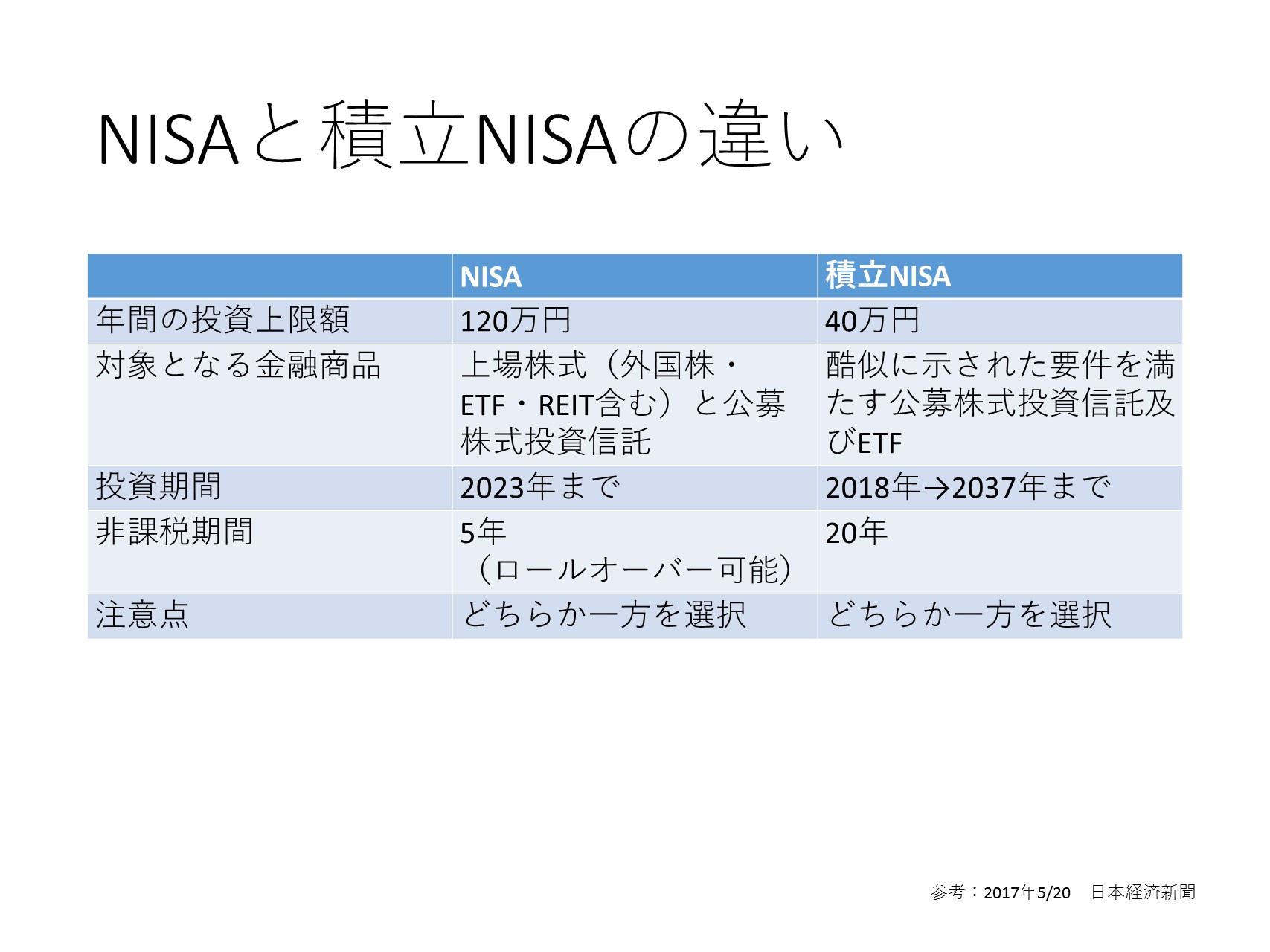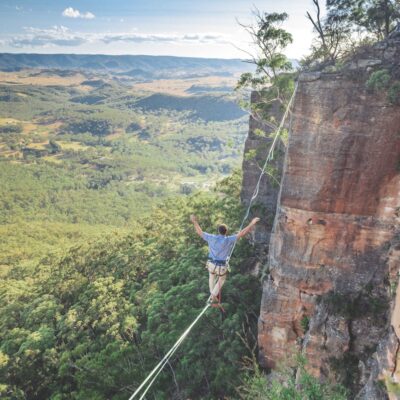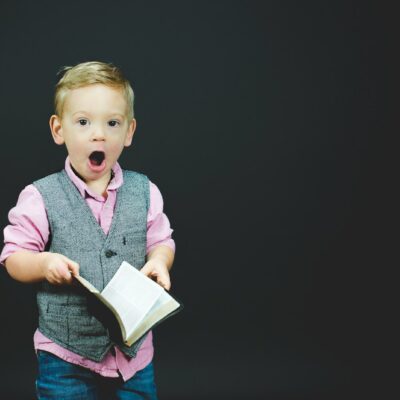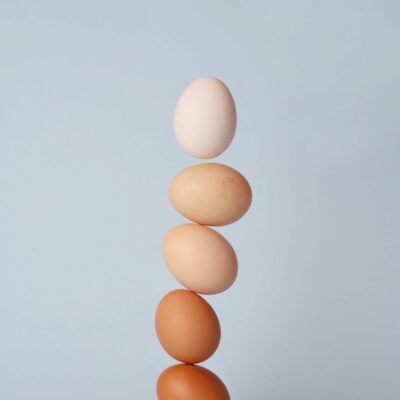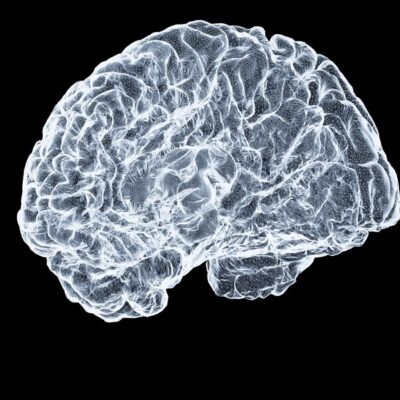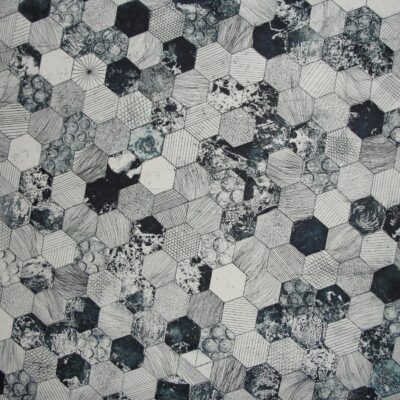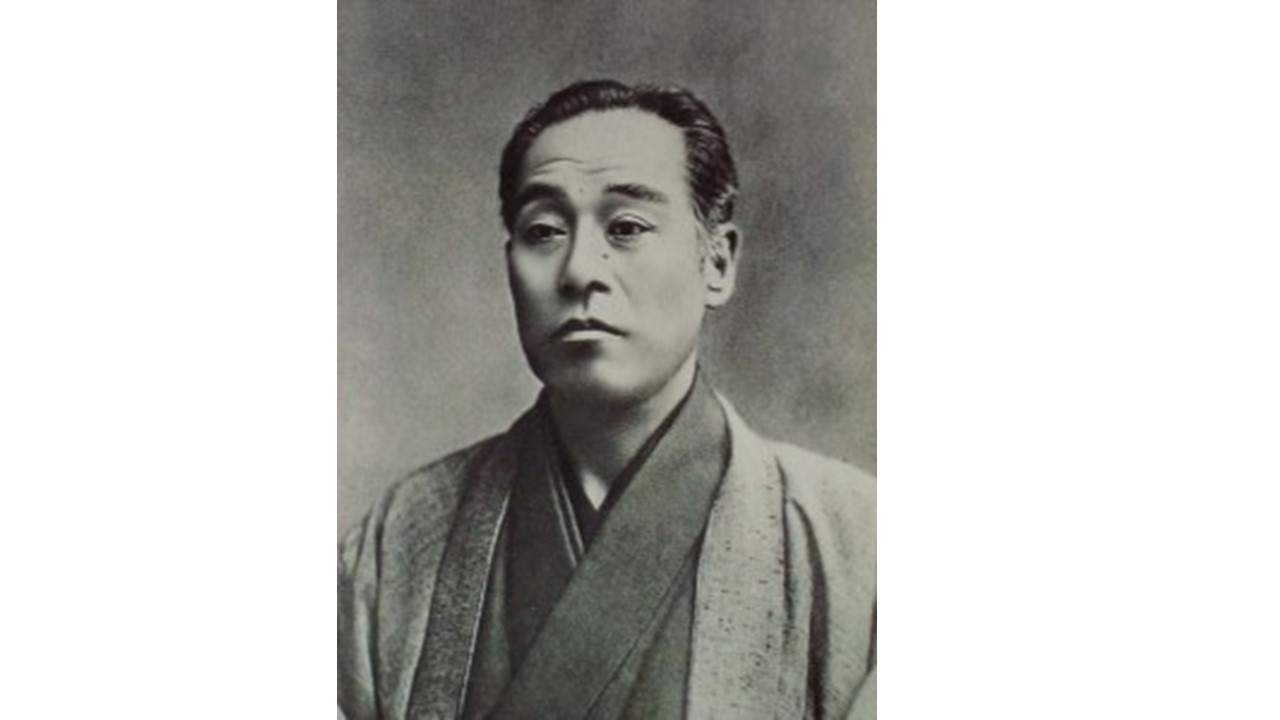Contents
裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)とは
こんにちは。
金融教育研究所の佐々木裕平です。
本日は裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)とは、について少しだけ記してみようと思います。
裁定というのは、金融の場合、「利ザヤを稼ぐこと」を意味することが多いと思います。
例えば、本来の価格が100円のものがあるとします。
でも市場ではそれが99円で売られています。
ということは、99円で買って、(その後、100円になった時に)100円で売ることで、1円の利益(利ザヤ)を稼ぐことができることになります。

裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)とは「ただ飯はない」ということ
裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)とは、「市場が仮に効率的ならばただ飯(フリーランチ)はないよねー」ということです。
どういうことでしょうか。
まず最初に、世の中にはただ飯はない、という点がポイントです。
これは、「うまい話を自分だけ見つけられないよね」ということですね。
まあ、当たり前ですね。
そのため裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)はノー・フリーランチ理論(無裁定理論)とも呼ばれるようです。

裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)でのさや取り(裁定取引:Arbitrage trade)とは?
効率的な市場では、「さや取り(裁定取引)ができまへんでー」となっています。
どういうことでしょうか。
別の言い方をすると、「ただ飯(うまいこと)はできまっしぇん!」ということです。
例えば、私がインターネット上でボールペンを買って、それを高く売ることができるでしょうか。
もしできれば、差額が利益となり(これをさや取りという)あっという間にお金持ちです。
でも現実には、みんなが価格競争をしているので、定価より高くは売れませんよね。
つまりただ飯は食えない。
また仮にボールペンの価格が低迷しているのなら、そのボールペンを買って、分解して、パーツを高く売ることができるはずです。
この場合も、もしできれば差額が利益となり、(さや取りできる)あっという間にお金持ちです。
でも現実には、もしそうなればあっという間にボールペンの価格が定価に戻って、やっぱり儲けられません。
やっぱりただ飯(ノー・フリーランチ)は食べられません。
こういうのを「市場が効率的」という風に言うことがあります。
効率的な市場においては、ただ飯・うまい話はない、ということになります。
金利も為替も、株価も理論上はただ飯が食べられないはず
そのため、金利も為替も、株価であっても、「私だけが有利に儲けられる方法・価格(ただ飯)はないよねー」ということになります。
これが裁定価格理論(APT:Arbitrage Pricing Theory)の前提だと思います。

市場には非効率的な部分と効率的な部分が混在している(濃度が変わりながら循環している?)
・・・というのが、経済学での理論上のお話、だと思うのです。
ところが現実は非効率的な部分があるとも、各種の研究結果が示しています。
それは行動経済学の分野では、人の持つ特性(一例:損失回避性)が影響を及ぼしていて、市場は効率的ではない、という考え方をします。
また、経済学では
「いやいや、そんなことないよ。やっぱり市場は効率的なはずだよ」
「どうして?」
「だって、非効率的な投資家がいるわけでしょ?」
「うん」
「だったら、利ザヤを稼ぐことができるわけでしょ?」
「まあ、そうだね。うまい飯が食えるね。だから、市場は非効率的でしょ?」
「いやいや違うっしょ。非効率的な部分、裁定取引の余地がある、ということは、機関投資家やヘッジファンドなどの効率的な投資家群などが裁定取引をするでしょ」
「たぶんね」
「じゃあ、結果として、うまい部分はすぐになくなるから、やっぱり市場は効率的になるでしょ!」
「うーん?」
という意見もあるようです。
筆者は最近、書籍などを読んでいて、市場は「概ね効率的なのではないか」という説が有力なのではないか、と思っています。
- 非効率的な部分(アノマリーなど)が割とある
- 裁定取引や、ある種の「その時だけは通じる(しかしすぐに通じなくなる)勝ち方」が少しだけ通用する
- でも、そんな彼らによって、市場の非効率的な部分は次第に減っていく
- しばらくすると、市場は「効率的な部分がたくさん増える」から、裁定取引やアノマリーがあまり通用しなくなる(→ランダムウオーク世界になる)
- そうなると、旨味が減るので、裁定取引者やヘッジファンドの力が弱まる(→結局、長期では市場平均が有利になる)
- 次第に市場は再び非効率的な部分が増えていく
- 結果として1に戻っていく
こんなふうに1~7の流れが、グルグルと循環していくのではないかと思います。
だから「市場は効率的でもあるし、非効率的な部分もある、でも長期的に見ると、おおむね効率的なのではないか」という風に、最近思っています。
それではまた。
いつでも、どこでも、だれでも、無料で、動画で学べる【お金の学校】のお知らせ
金融教育研究所の【お金の学校】をYouTubeにて継続的にアップしています。
ブログ記事よりも、よりわかりやすく、学びやすくなっています。
よろしければ、ご覧ください。
また、チャンネル登録や「いいね」をしていただきますと、とてもうれしいです!
どうぞよろしくお願いいたします。





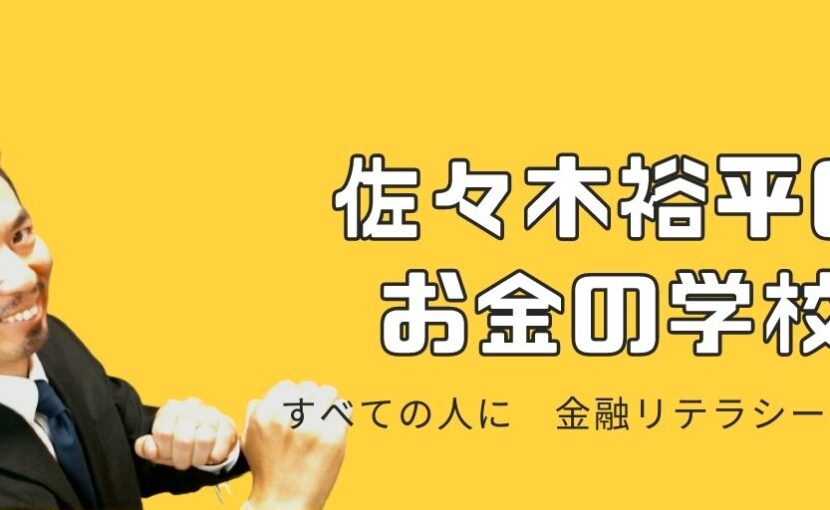







_001-250x250.jpg)
_001-1-250x250.jpg)
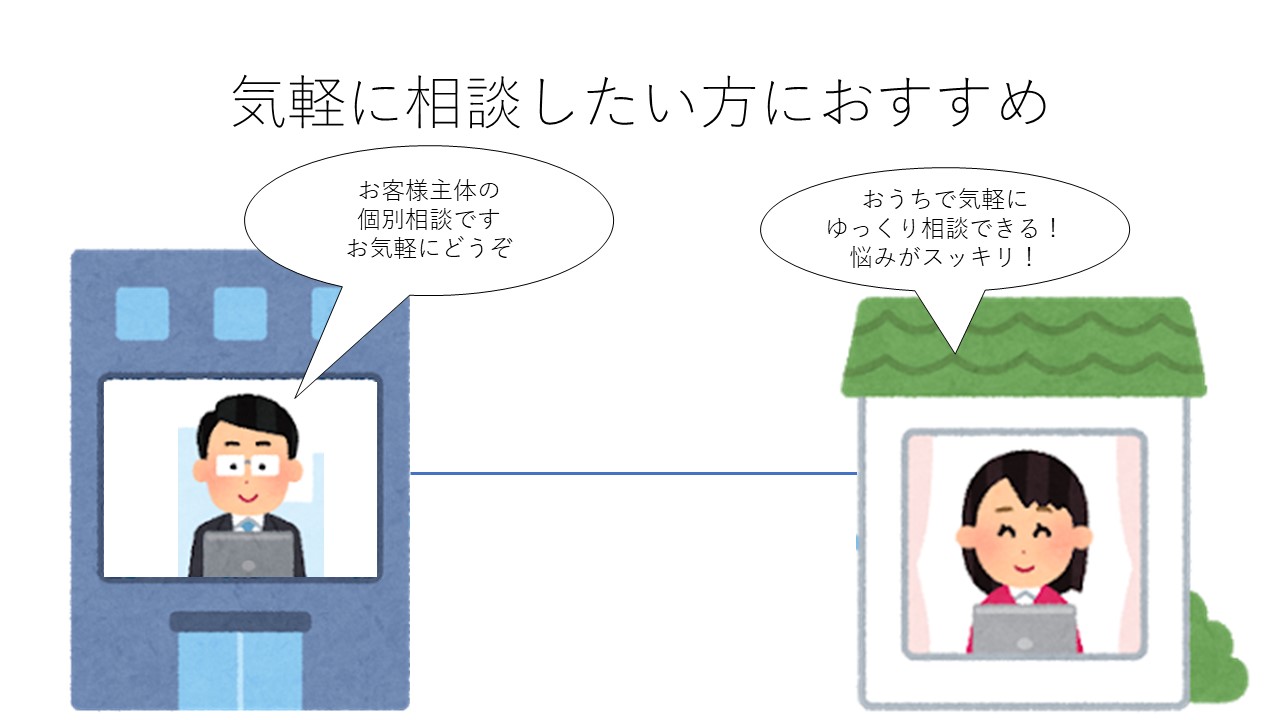

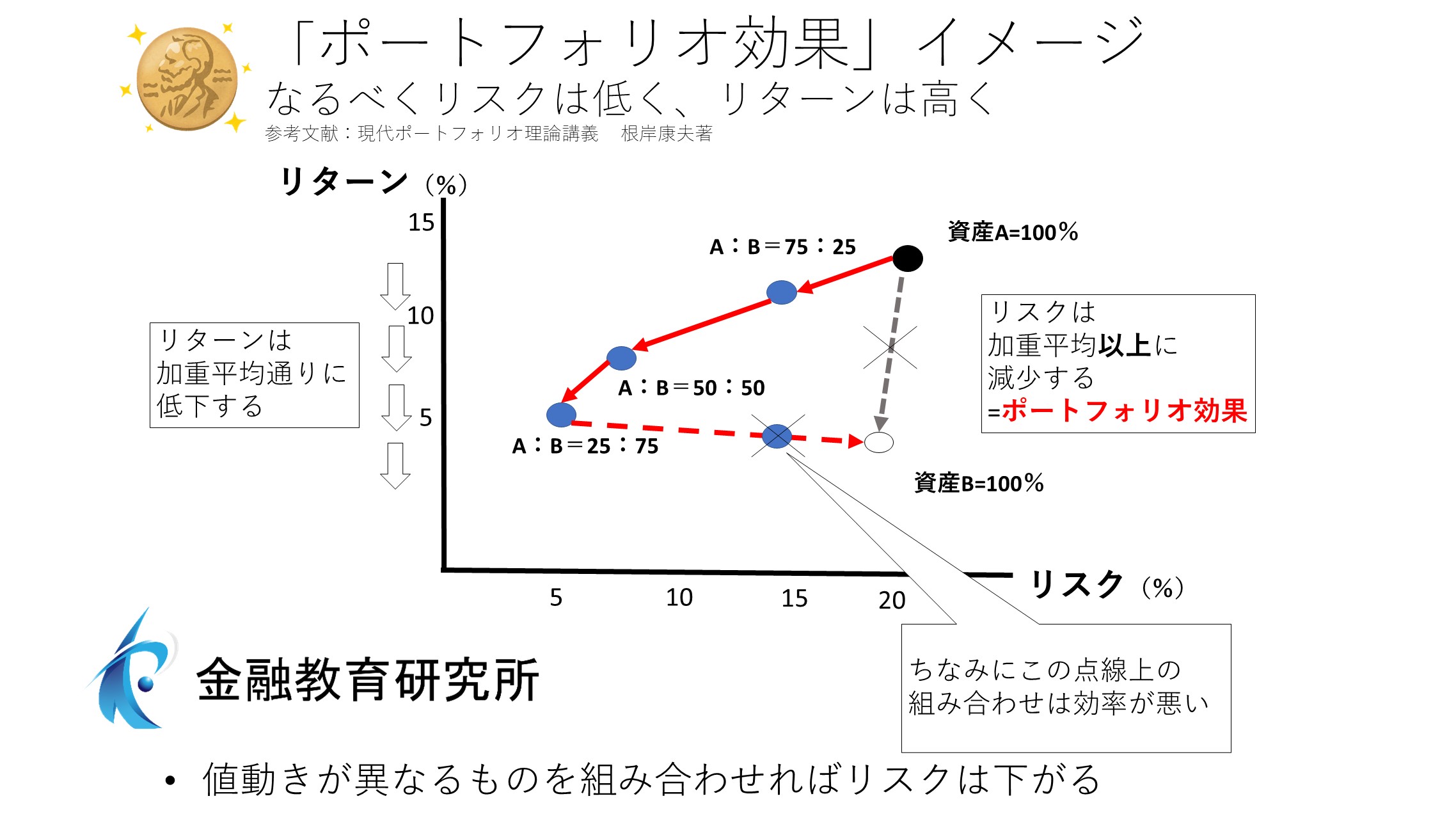



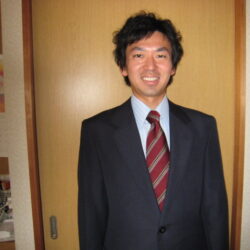
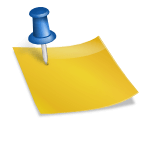
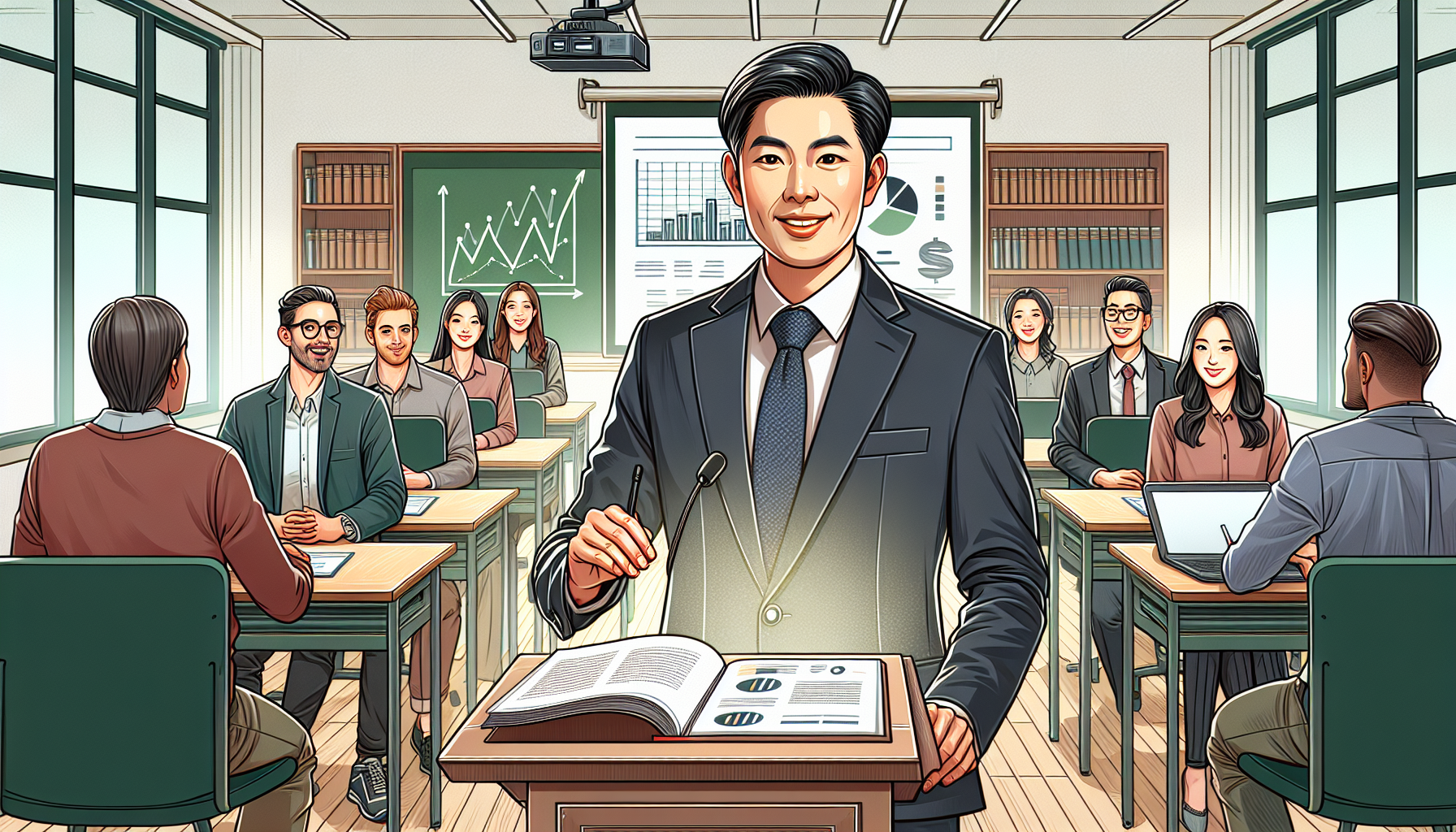

_001-724x1024.jpg)