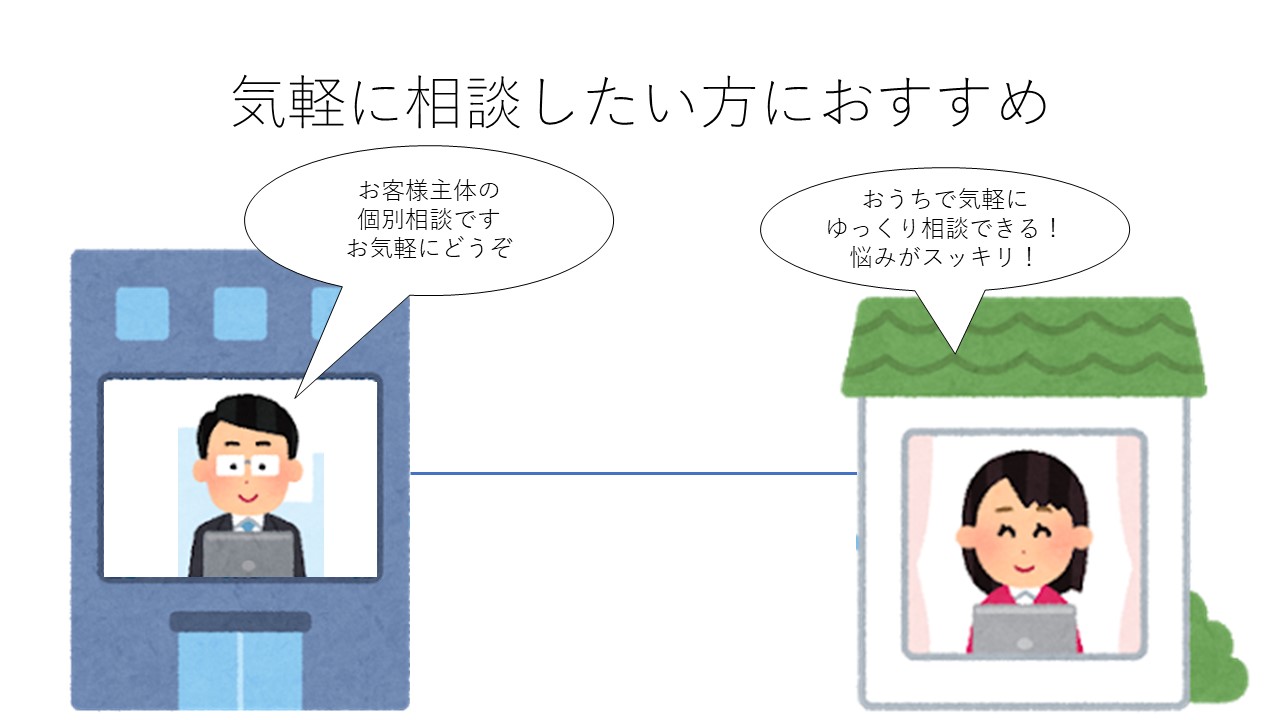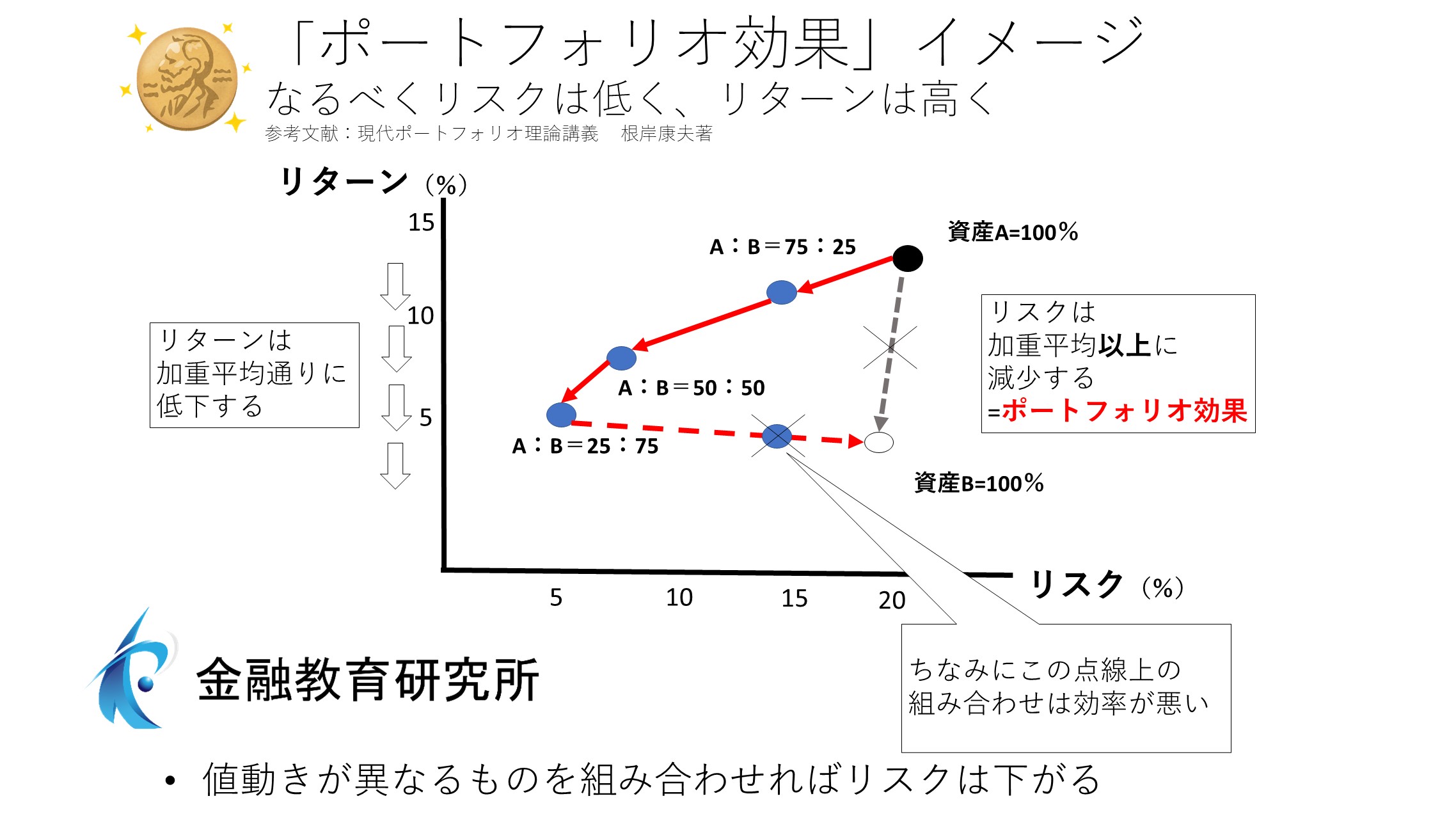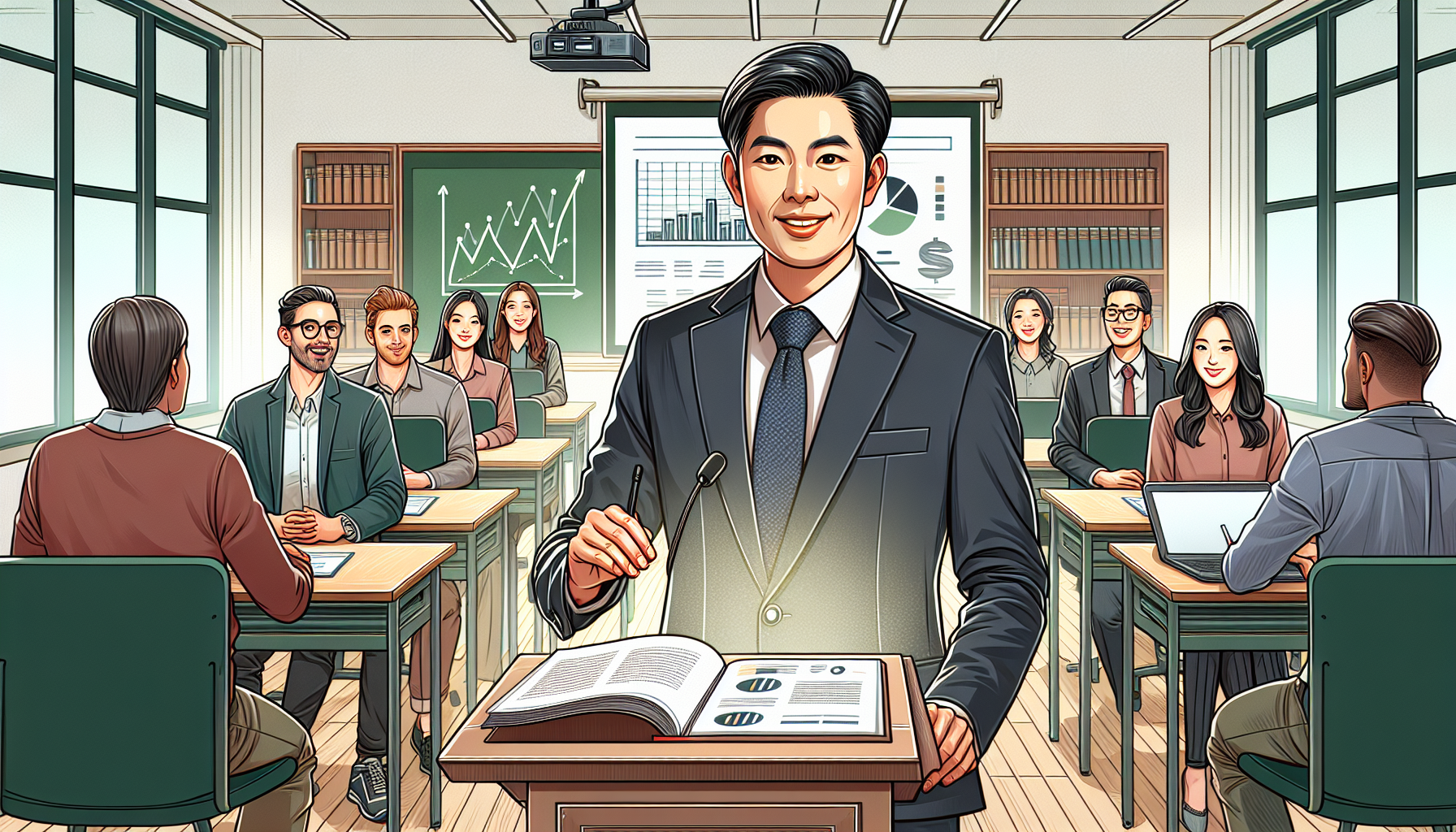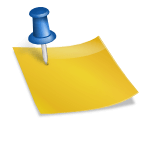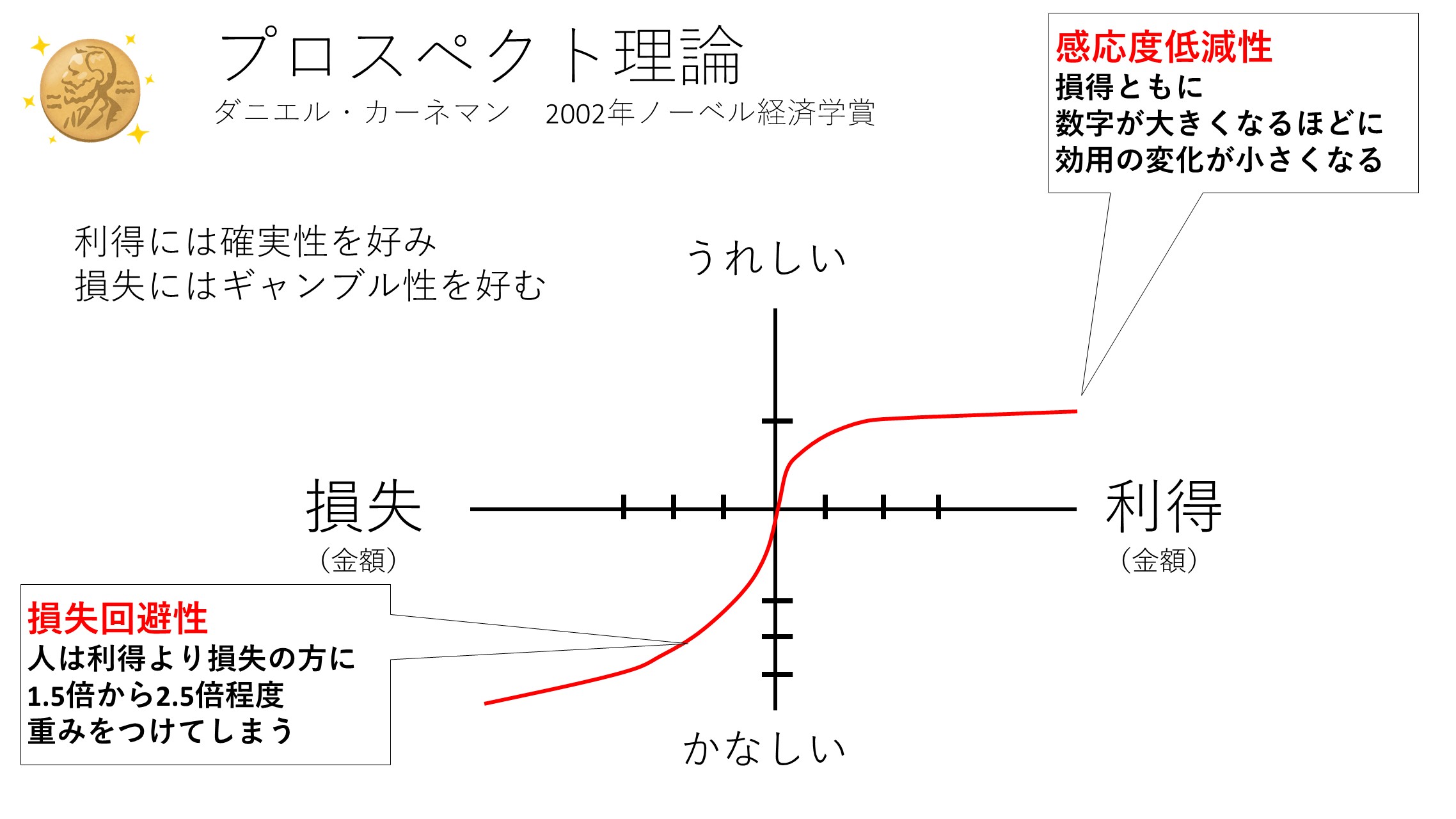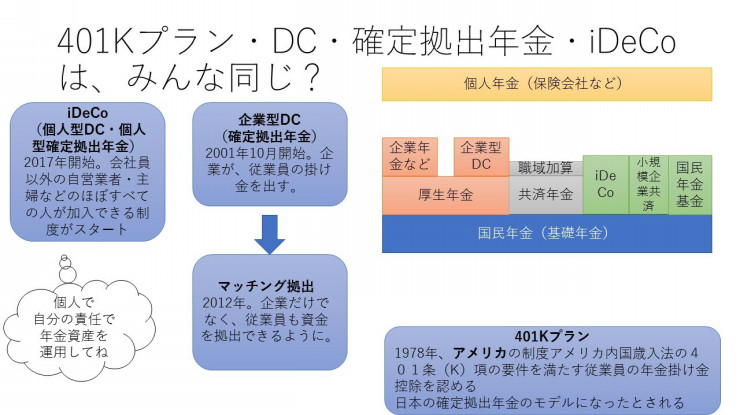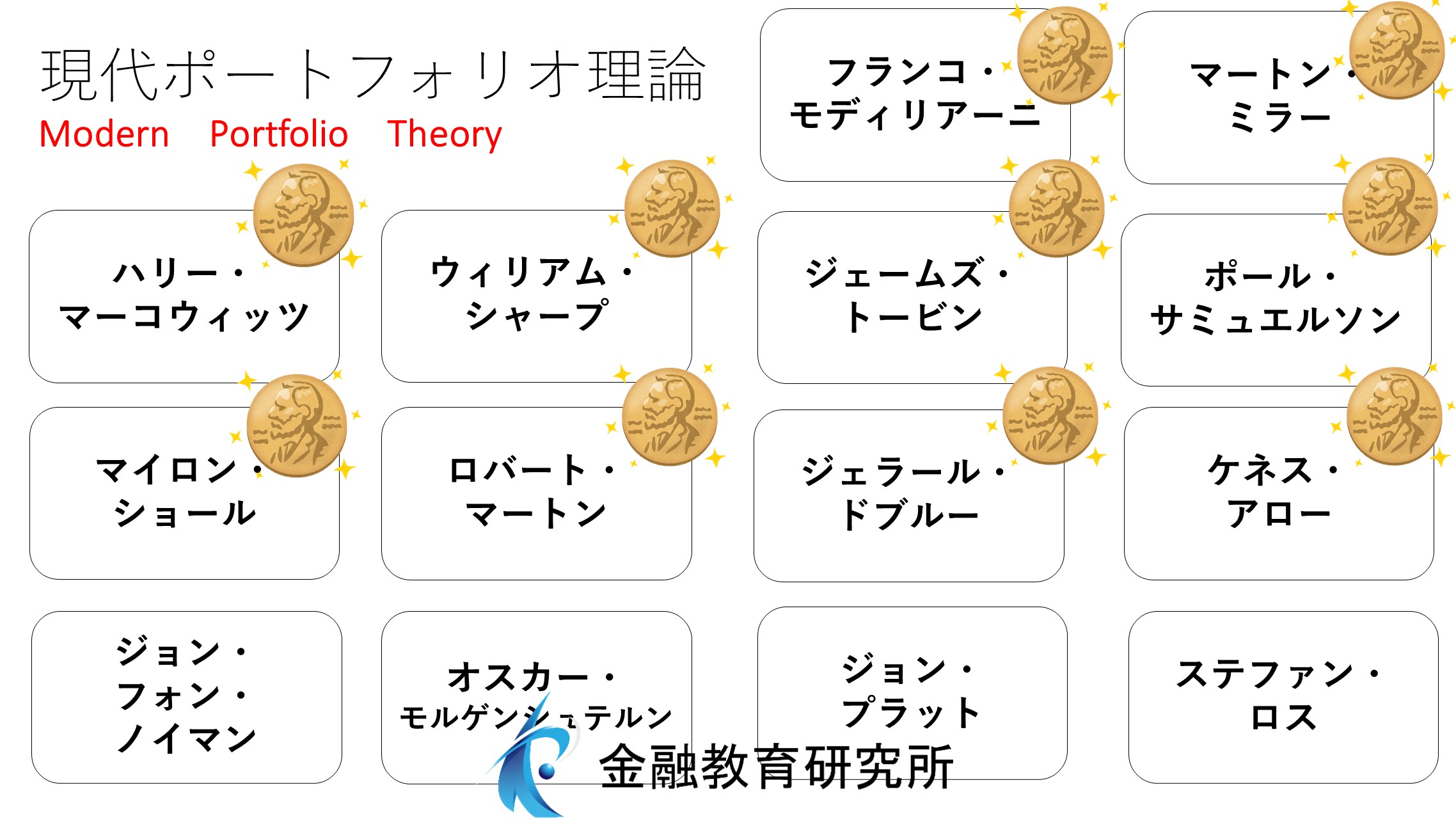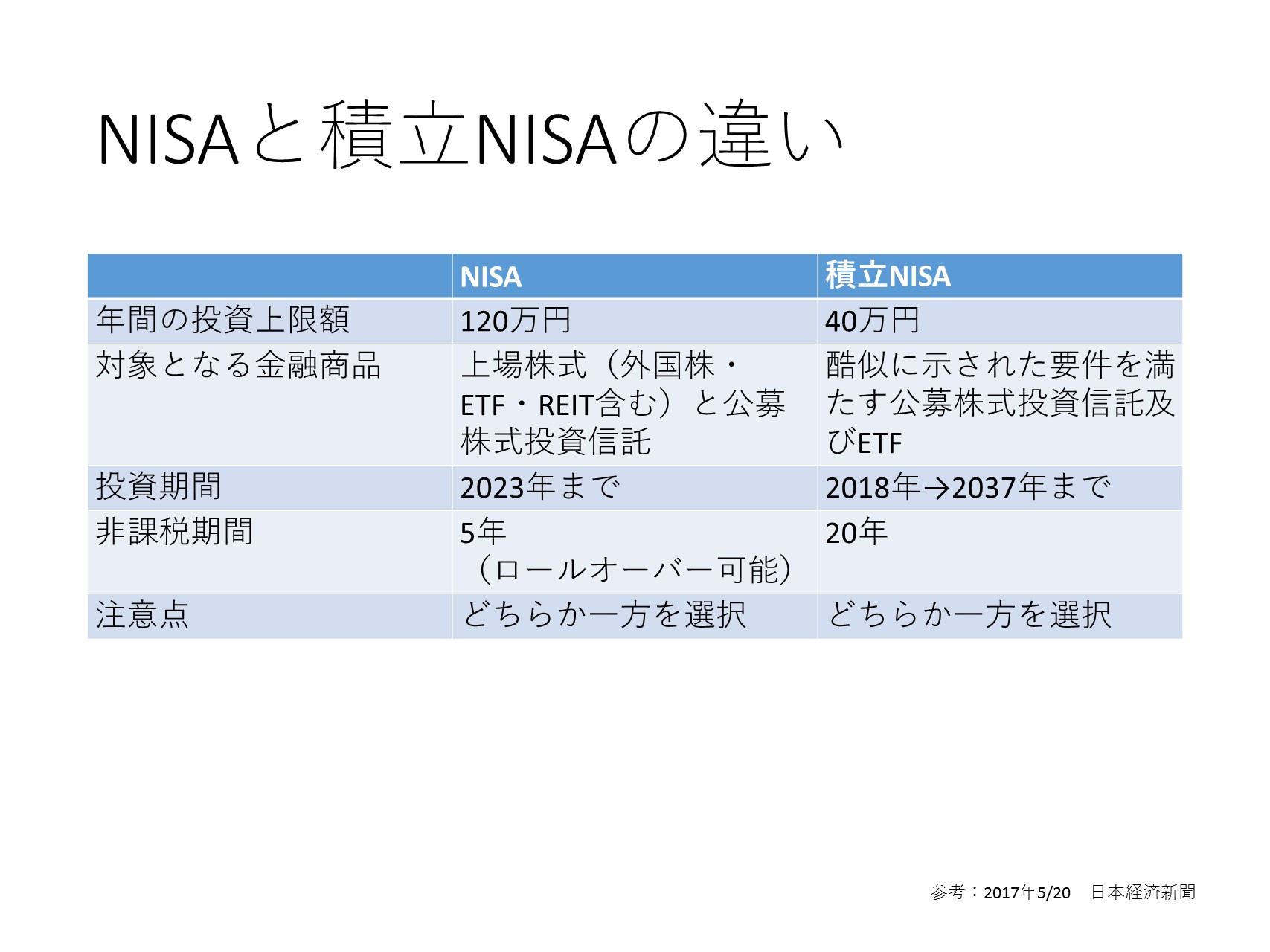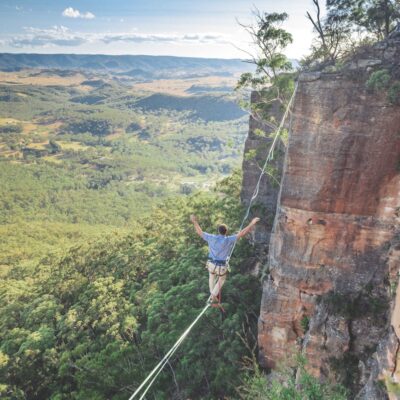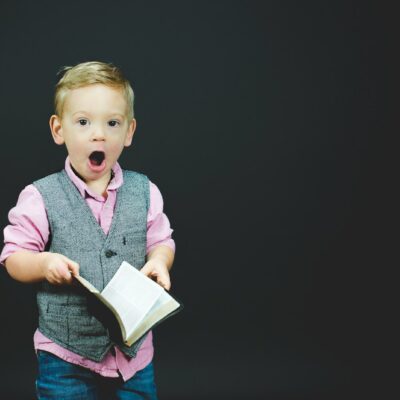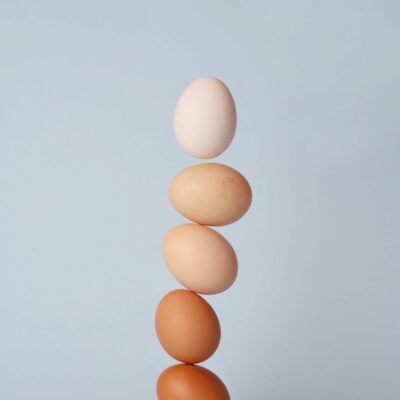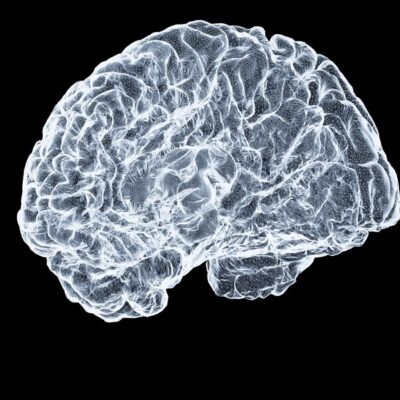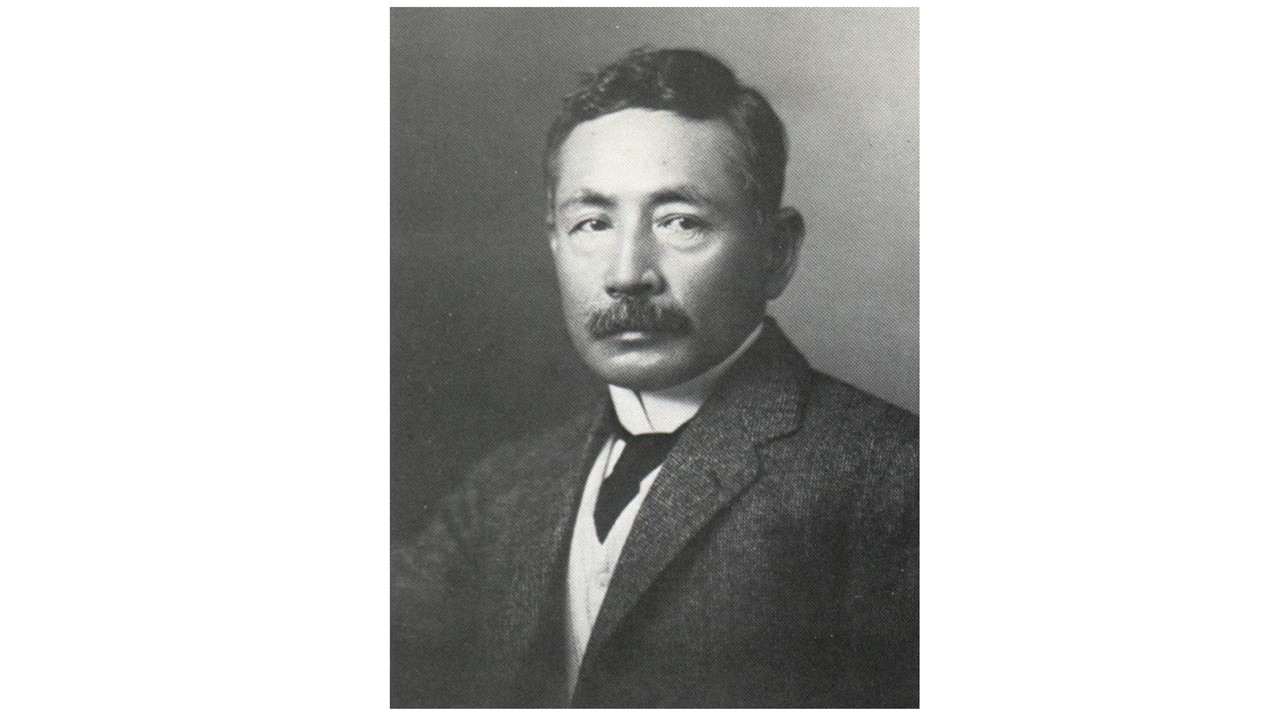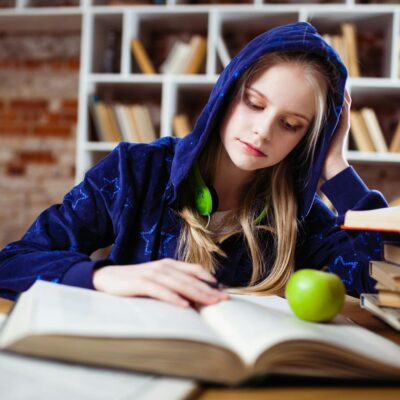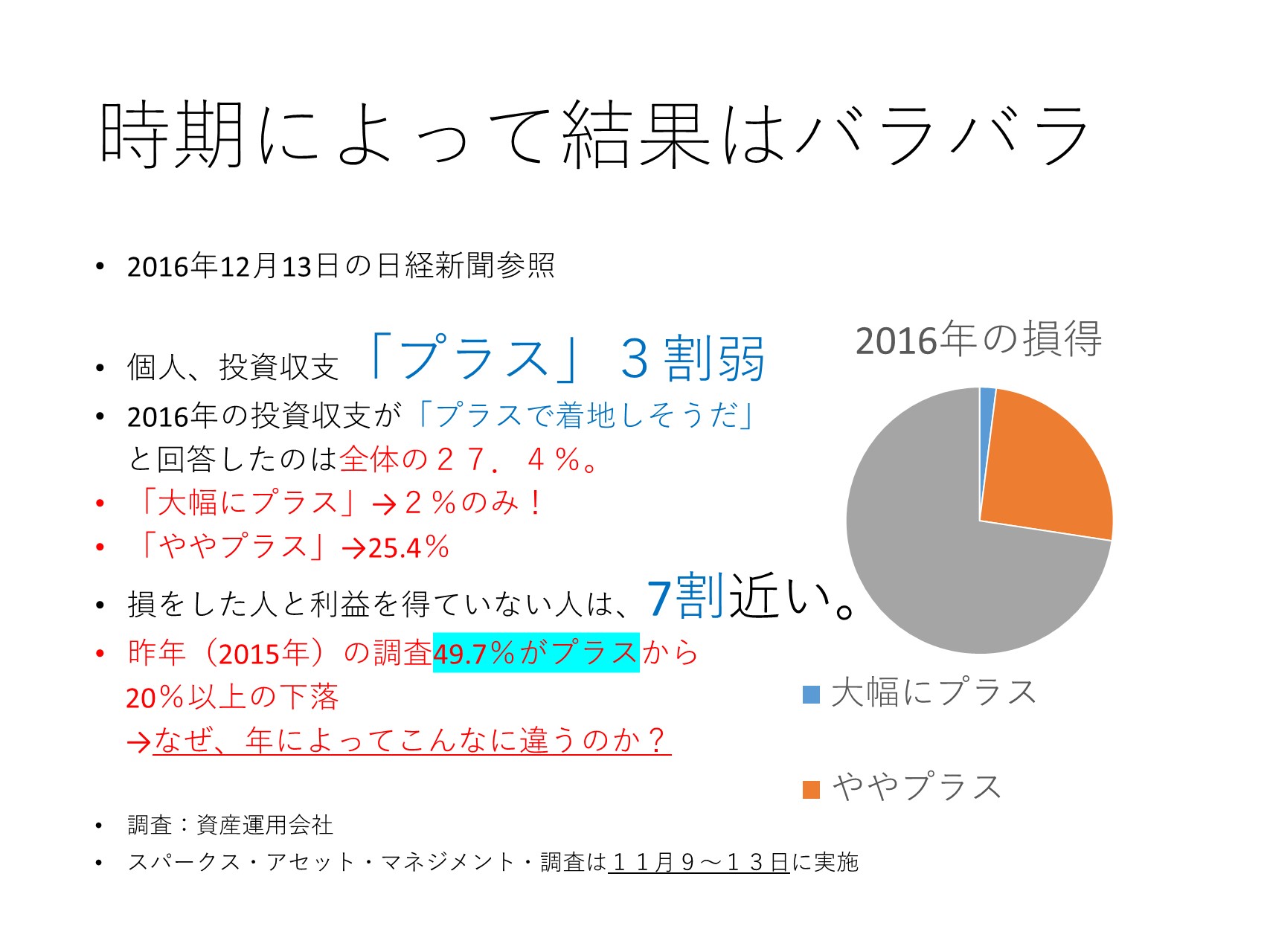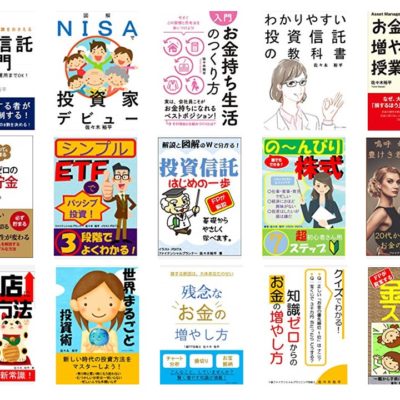Contents
知ってるようで知らない、公的年金って、いったい何?
金育研究所は金融リテラシーの普及・啓もうに努めています。
専門は「投資による合理的な資産形成」です。
本記事は、お金の知識教育(金育)の一環として記すものです。
個別具体的な相談は、お近くの日本年金機構の事務所へどうぞ。
今回は、公的年金について見てみましょう。
毎月、お金を収めているけど、どんな仕組みなのでしょうか?
また、どのような種類があるのでしょうか?
その他の年金などの種類も見てみましょう。
年金制度は大きく分けて、2種類!
まず、年金の制度は、大きく二つに分けられます。
- 公的年金
- 私的年金
この二つです。
公的年金と私的年金の中身
公的年金には、
- 国民年金
- 厚生年金保険
- 共済年金
があります。
本日は、これらの公的年金の中でも、
国民年金と厚生年金保険について詳しく見てみましょう。
そして、私的年金には、
- 企業年金
- 個人年金
があります。
こちらは、またの機会に見てみましょう。
国民年金っていったい、何のこと?
国民年金は、
基礎年金
とも呼ばれます。
- だれが?→ すべての人
- いつまで?→20歳以上60歳未満
主婦や、自営業者・自由業・学生などが当てはまります。
厚生年金保険の対象は?
- 誰が?→ サラリーマンや公務員
つまり、およそすべての人は、国民年金に入り、
そのうえ、さらに
サラリーマンや公務員などは、厚生年金にも加入している、ということですね。
これだけを見ると、
仕組み上、サラリーマンや公務員の方が手厚いイメージであることが分かります。
(自営業者などは、その足らない部分を、何らかの形で準備しておかないといけないのですね)
厚生年金保険の給付はいつもらえる?
では、サラリーマンや公務員の加入している、
厚生年金保険の給付はいつもらえるのでしょうか?
それは、対象者が
- 老齢
- 障害
- 死亡
の状態になった時に受け取れます。
国民年金はシニアになったら、いくらもらえる?
およそすべての人が加入する国民年金ですが、
65歳になったら、いくらもらえるのでしょうか?
2018年現在のもらえる価格は基本的に
- 77万9300円
のようです。
(変わっていきます)
12か月で割ると、
毎月当たり、
- 6万5千円程度
ですね。
※会社員や公務員の場合は、これに老齢厚生年金がプラスされます。
一般的には、現時点で合計22万円程度になるようです。
これだけで、毎月生活できる人は、少数派だと思います。
あなたがシニアになった時に「毎月6万円で生活してね」
と言われたら、困りますよね。
その差額分の生活費などを
- シニア時代も働く
- 預貯金でカバーする
- 資産運用で補う(うまく行った場合)
などでやりくりしないといけないのですね。
知っておきたい障害給付
障害基礎年金という制度があります。
※後述しますが、障害厚生年金という制度もあります。
障害基礎年金は、ものすごくザックリいいますと、
障害を負った場合に年金が受け取れる仕組みです。
もちろん、年金を収めているなどの条件はあります。
ただ、とても優れているセーフティネットですので、
できれば、万が一の事態に備えて、国民年金は収めておくようにしたいところです。
知っておきたい障害厚生年金
こちらも、大変にザックリ言いますと、
厚生年金保険に加入している方が
障害を負った場合に受け取れるものです。
やはり、加入者が会社員や公務員などですので、
国民年金だけの自営業者などよりは、手厚いイメージですね。
シニアになる前に亡くなったらどうなる?
遺族給付という制度があります。
条件はありますが、
- 子のある妻
- 子
が遺族基礎年金を受給できます。
また、寡婦年金という制度もあります。
寡婦とは、馴染みのない言葉ですが、
ウイキペディアによりますと
寡(やもめ)・寡婦(かふ、やもめ)・寡夫・寡男(かふ、やもお)とは配偶者と死別または離別し、再婚していない独身者のことである。口語的な別名では女寡(おんなやもめ)、男寡(おとこやもめ)、後家(ごけ)、未亡人(みぼうじん)[1]などがある。寡婦を支援するための、税制上の優遇や公的な援助制度などが設けられているが、寡夫を支援する制度は皆無である。
となっています。
そしてもちろん、
厚生年金にも遺族厚生年金があります。
まとめ
障害年金や遺族年金などは、
いざというときに頼りになりますので、
国民年金には最低限加入(納付)しておいた方が良い気がします。
また、
国民年金だけしか入っていない自営業者
などは、
国民年金+厚生年金に加入している会社員や公務員と
比べると、どうしても、受給額が見劣りします。
できるだけ早いうちから、
貯金や投資での資産形成をスタートすることが重要ではないでしょうか。
また、会社員や公務員の方も、
老後の生活をより充実させるために、
積み立て投資などで準備をしておく必要があるかもしれません。
◆お礼とお知らせ
拙著 入門お金持ち生活のつくり方(こう書房)
が、Amazonさんの電子書籍ランキングで
人生論・教訓・自己啓発・倫理学・道徳部門で1位となりました。
おかげさまで2月中、連続1位となりました。
関係者・読者の皆様に、厚く御礼申し上げます。
ポリシー
金育研究所は設立以来、
金融商品・保険商品の販売・勧誘・斡旋はしていません。
常に中立・公正な立場から、
合理的な金融リテラシーの普及・啓もうを行っています。
お金と投資の知識教育(金育)は、およそすべての人にとって
必要なものですが、
残念ながら、現在の義務教育のカリキュラムには入っていません。
多くの方が、投資に対して
- 困った勘違い
- 勿体無い行為
を行っています。
長期分散投資であっても、
多くの方が、勘違いをして、損な行動をしているのが現状です。
合理的な金融リテラシーが普及すれば、
結果として、社会が少し明るくなるのではないか? と考え、
行動しています。
小さな事務所ですが
これからもコツコツと金融リテラシーの普及・啓もうに努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
金育研究所メニュー
投資セミナー
個別相談
個別相談 料金
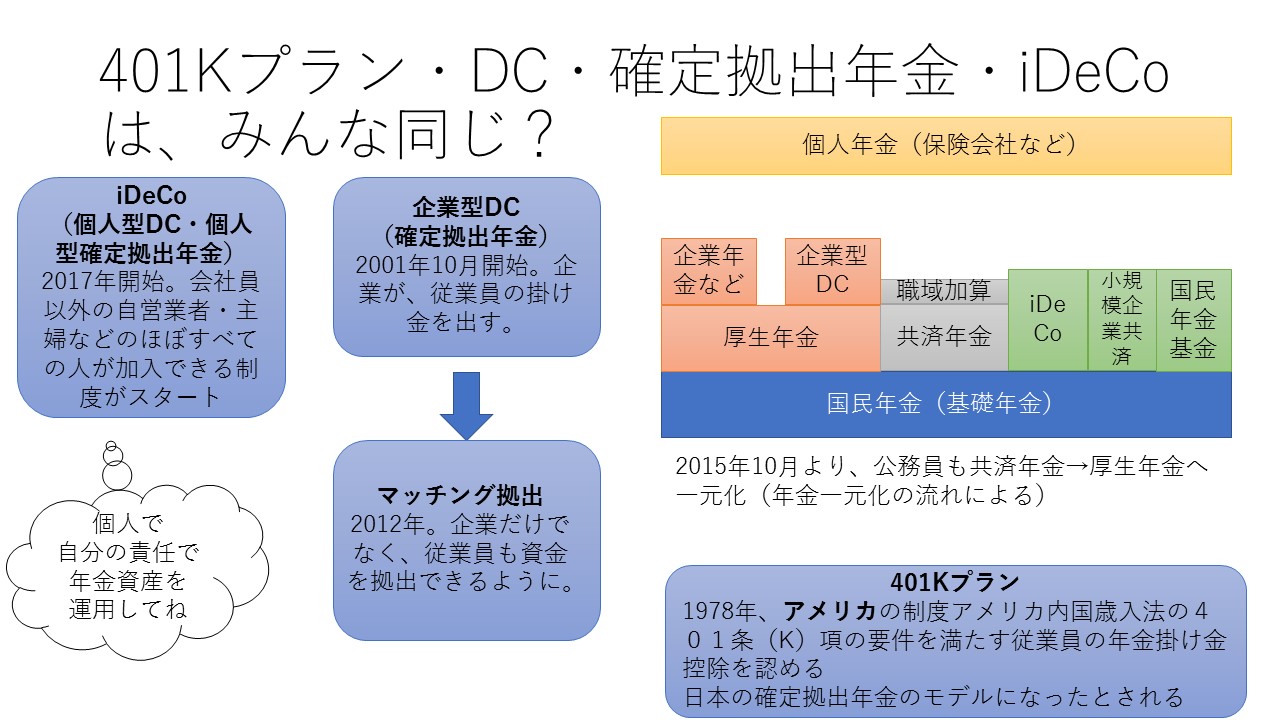

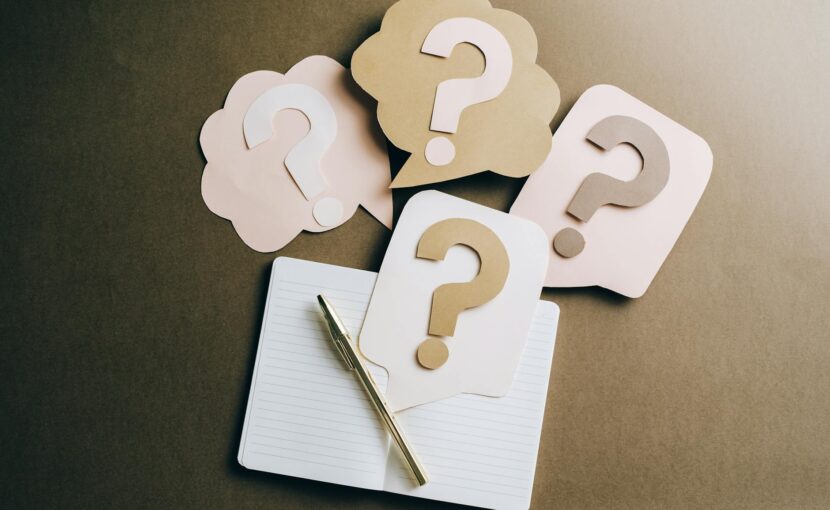








_001-1-250x250.jpg)
_001-250x250.jpg)